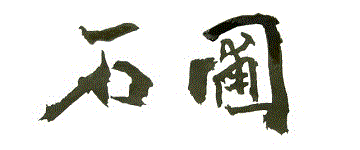同時代に生きる幸福
「ベトナムでタクシーに乗ると70年代のアメリカンポップスばっかり流れてる。当時戦争していた敵国の音楽を流すとはどういうことなのか?」と辛坊治郎がテレビで語っていた。
70年代、80年代、90年代の初めごろまでアメリカのヒットチャートをノートにとりながら聴いていた。思い返すとやはり70年代は楽曲の質が特別高い。敵の音楽だろうがいいものはいいのだ。
セブンイレブンにはBGMが流れていて、誰が選曲しているのか知らないがやはり70年代アメリカンポップスばかりだ。ある時は Love Will Keep Us Together、ある時はRain Drops Keep Falling On My head、ある時は Send One Your Love。前二曲は日本でもヒットした(そう、当時洋楽はよく売れた。今では考えられない)ので当時を知る人は多いと思うが、最後の曲なんかスティービーワンダーも全くプロモーションしなかったほぼ全く売れなかった曲だ。スティービーが神だった当時の私には、全く売れ線を狙っていない曲作りに驚きもしたし、次のアルバムでは彼の音楽的才能が枯渇したのを感じ取って、最後の名曲になってしまった思い出の曲でもあった。
70年代といったら、今日Queenくらいしかよく知られていないようだが、Elton John もいたし、Led Zeppelin も活躍していて、ロックが輝いていた。商業音楽も台頭していたし、黒人音楽からディスコサウンドが生まれ、一方全く売る気がなく、生まれるべくして生まれてしまった表現として極めて純粋な優れた楽曲が多数存在した。Sly Stone がチャートの1位になるなんて今では全くあり得ない。奇跡の時代だったのだ。
多感な10代にそんな経験をしたことは、今にして思えば人生で最高の幸運だった。率直に言って1990年代以降の音楽はほぼゴミだ。何を表現したいのか皆目理解できず、ただただ売れ線ばかりを狙っている。日本においては人生の応援歌ばかり。そんなに人生に行き詰ってんの? また、行き詰ってる大衆を応援できる君って誰? 神? ま、椎名林檎と山口一郎は認めるけどさ。
多感な70年代に巡り会ったもう一つの幸運は漫画の革命に居合わせたことだ。花の23年組といわれる少女漫画家たちが少女漫画を舞台にテーマ、コマ割り、絵柄などに競うように新しいものを持ち込んだ。女きょうだいの多い自分は一冊も買わずに次々とその衝撃を味わうことになった。
萩尾望都、大島弓子(文化功労者おめでとうございます。新聞発表でも堂々と写真掲載拒否を貫き、いつもの自画像素晴らしいですね)、竹宮恵子、おおやちき、三原順などが人気作家だった。三原順なんかあんな難解な人間関係の漫画をよく大衆誌に掲載したもんだと思う。ついて行ったコアなファンが多数いたことも今では驚きだ。難解といえば大島弓子のバナナブレッドのプディングも問題は何一つ解決していないのに何故かハッピーエンド、何故?今でもわからない。そんな少女漫画を読んでいたら、少年漫画の精神年齢のあまりの低さ、単純な説明的な絵、勢いだけの汚い描線、ジャンプなんか読めたもんじゃなかった。
自分の一番のお気に入りは山岸凉子だった。名作アラベスクでカリン・ルービッツなる不思議な女を登場させて以降、妖精王のクイーンマブ、短編群の女主人公とテーマがどんどん深化し、天人唐草ではついに発狂し、スピンクスでは狂った母が子供を追い詰め、メデューサでは気が狂っていることを自覚するに至った、その一連の展開は本当に息を呑む思いで読んだものだ。表現するとはどんなことなのかこんなに優れた教科書はなかった。もっとも当時は教科書としては接していない。強烈な読後感を味わいたかっただけだ。大島弓子に続いて顕彰されることを期待している。 ('21.10.27)
言葉のこと
建築家の伊東豊雄は近著で「自分の身体性は、言語によって作られたと思っています。日本語で思考してきたことと、身体性は深く関係していると感じます。(中略)振り返りながら考えていくと、曖昧さが自分の性格でもあるし、本質的な自身を形成していると思います。それは日本語の持つ曖昧さによるところが大きい。」と述べている。
伊東の主眼は曖昧さを以て西洋一元主義に揺さぶりをかけたいとするところにあるのだが、私には言語が身体性に関与するという認識のほうが興味深く思われる。
言語は言うまでもなく意味するものとの完全な1対1の対応をしているわけではない。人によっても違う(だから誤解が生ずる)。時代によっても変わる。語のほうが変わることもある(「行かれる」という語が変だと関東人は主張する。can go ではなく別の意味にしかならないらしい)。
こんなに不完全なものなのに、「寸鉄人を刺し」たり、虐めの言葉が自殺に追い込んだりもする。逆に幸せにもする。
今日書は展覧会至上主義で、見栄えのする文字のある詩を選んだり、書きにくい文字を避けたりする。これは結局文字を書いているのだ。せっかく言葉を書いているのに言葉の武器を利用しないとは、藝術として何ともったいないことをしているのかと思ってしまう。 (’21.9.1)